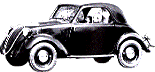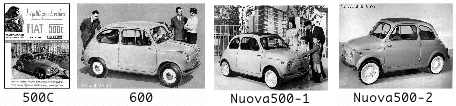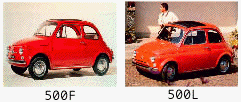|
Topolinoの発表
FIAT500の前身、いや元祖である500Topolinoが発表されたのが1936年のこと。
それは、庶民にとって高価で夢でしかなかった自動車が、誰にでも手の届くミニマムトラスポーターとして世界的な大反響と共に人々に受け入れられた。水冷直列4気筒SV569cc2人乗り、最高速度は85km/hと、小さく非力ながらも元祖500は、安くて維持していくにも大きな負担にならない経済性、さらにその愛嬌あるスタイリング(Topolino=はつかねずみの意)から大ヒットとなった。
そして、その卓越したセンスと技術でこの戦前の傑作を作ったのが、その後35年以上にわたってフィアット設計技術部門を支えた故ダンテ・ジアコーザ氏である。

リアエンジンの時代 NUOVA500誕生
敗戦という混乱の中、500Topolinoは、500B、500Cと改良を続けながら20年近くも生産され続け、1100B、1500D等といった戦前モデルの改良型と共に復興の足掛りとなった。
しかし、 本格的な戦後型の開発にはしばらくの時間を要した。そこで進められていたのがTipo100とTipo101という2つのプロジェクトであった。ここでもジアコーザは手腕を振るい、Tipo101は初のモノコックボディの1400として1950年に発表された。
ところが残るTipo100の開発は難航する。これからのスモールカーにFRは相応しくないと考えていたジアコーザは、当初FFを採用する予定だった。しかし信頼性やコストの面からFFは断念、そこでジアコーザはRRによる画期的なラゲッジ・レイアウトの水冷直列4気筒633cc、600[セイチェント]を1955年に完成させた。それと同時にもう一つ新たなプロジェクトも始まっていた。その名は「Tipo110」。戦後の庶民は、もっと手ごろで小さなクルマを求めていた。大衆は、新しい500を待ち望んでいたのである。(正確には600がトッポリーノの後継車だが、名前とその役割的見地から、あえてここではNuova500を後継車としています。)
こうして1957年、600のノウハウを基に空冷直列2気筒OHV、479ccという必要最小限のまさに庶民のクルマ、Nuova500[ヌオーバチンクエチェント(Nuova=新しいの意)]は誕生した。
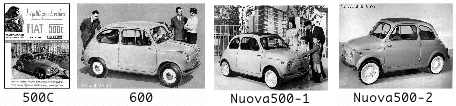
イタリアを埋め尽くすチンクエチェント
600と500は大ヒットとなり、とくに500はそれまで自動車というものに縁がなかった人々や、地元から一歩も出ることなく一生を終えてしまうような人も多いイタリア人の生活をも変えてしまう程であった。そしてイタリア中を埋め尽くした。
600はその後、3列シート6人乗り(2列シートも有)の600Multipla
[ムルティプラ] を追加し、600D、850と改良されながら1969年まで生産され続けた。
500は1958年、排気量を499.5ccへ拡大した500Sport
[スポルト] を追加。馬力は15HPから21.5HPとなり、トップスピードも85km/hから105km/hへとアップした高性能モデルである。
1960年にはスポルトのエンジンを18HPにディチューンした 500Dに移行し、同年、ステーションワゴンの500Giardiniera[ジャルディニエラ]を発表。
1965年からは駆動系の強化と、ドアを後ヒンジから前ヒンジに、その他細部に変更を加えた500Fに進化し、3年後にはより内外装を豪華にした(バンパーパイプやフロアカーペット等)500L(Lusso=豪華・贅沢の意)を加え、1970年生産台数は全盛期を迎える。

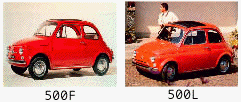
チンクエチェントよ永遠なれ
しかし、15年にわたり、イタリア庶民の夢と生活を乗せて走り続けた500にも、やはり時代の流れが押し寄せてくる。暮らしが豊かになるにつれ、人々のニーズはより大きく、高性能なクルマを求めはじめていた。
1972年一旦生産を中止した500は、後継車としてボディサイズもやや拡大され、より現代的でスクエアなデザインの126にその座を譲った。126は基本的に500をベースにしながら、エンジンは594cc、23HPへとアップされ(1977年からは652cc、24HP)、室内空間やラゲッジスペースも拡大された。
ところが一旦はその役目を終えた500だったが、根強い人気は衰えず、フィアットはしばらく500R(Revise=改訂版の意)として存続させることにした。エンジンは、126の物を18HPにディチューンして使われ、内外装はFタイプに多少変更を加えた物だった。(エンブレムやホイール等)
結局500Rは1975年まで生産され、これを最後に500はカタログから姿を消した。18年間という永きにわたり愛され続け、300万台以上を産んだFIAT500。126やPANDA、A112、そしてNew
CINQUECENTOと形や時代は変わっても、その小意気な魂は永遠に受け継がれてゆくだろう。

|